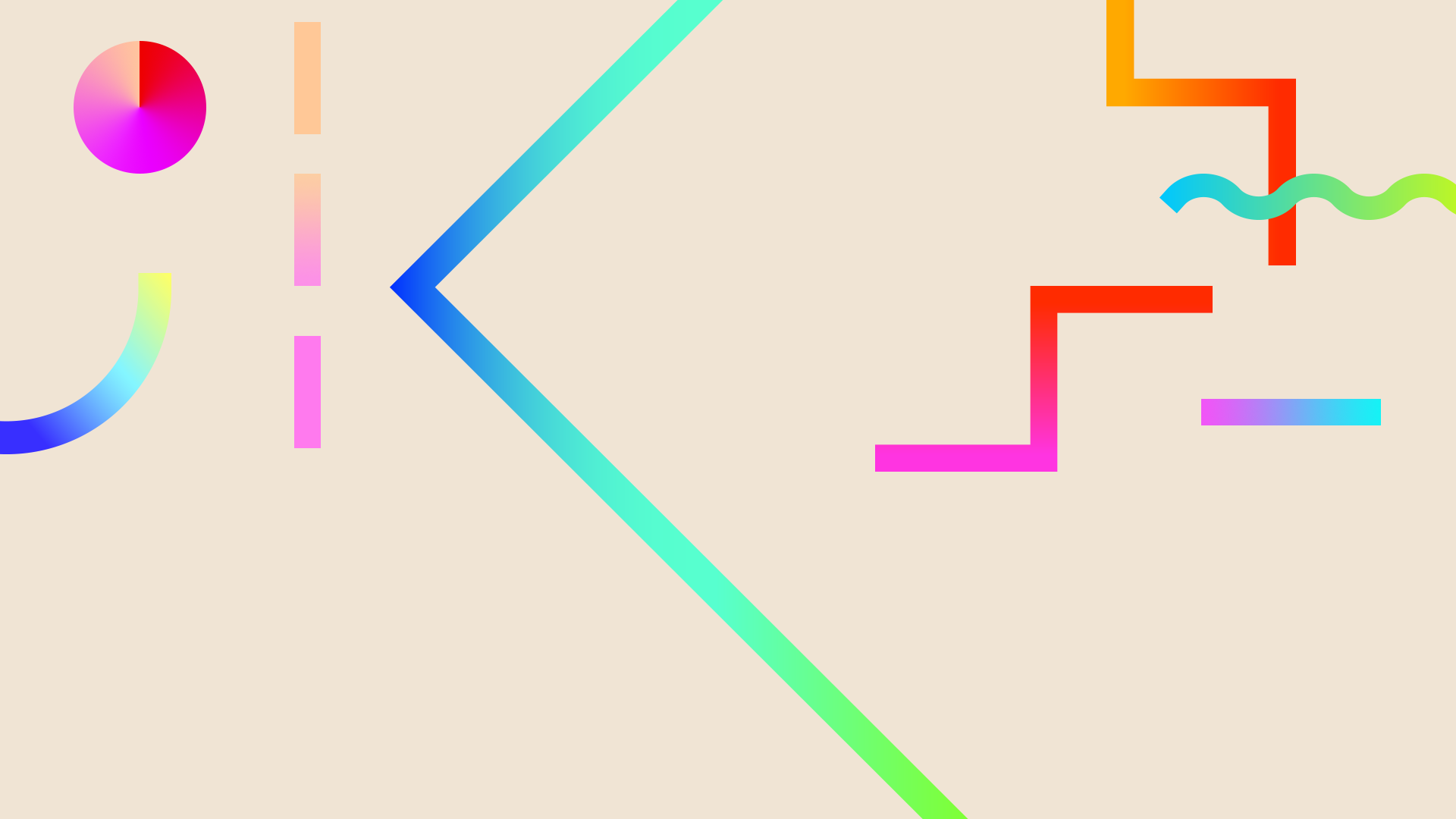要る / 要らない / 保留(31-1)
2008年、仕事を辞めました。そして、まず取りかかったのは、父と私の今の暮らしに合うように物を片付けることでした。2002年に母が亡くなるまで、自分の部屋以外は母が統治していましたから、開けたことのない天袋はいくつもありました。...


クレソン摘み
1994年の3月、父が脳塞栓で倒れて少したった頃、ちょうど今の季節、大学の同級生二人が父の見舞いに来てくれました。そして、病室から片時も離れられずにいる私を、病院からそう遠くない湧水の小川に連れ出してくれました。 早春の柔らかな緑、陽は西に傾き始めていました。...


住宅環境整備(30-6)
母の応援もあって、社会に目を向ける機会を持ちましたが、その母が2002年急逝しました。それからのすったもんだは、これまでお伝えしてきた通り。自分の生活の中に父の生活がすっぽり入る形になりました。そんな時間と経験を経て、また生活の形は変わりました。さてさて、これからどうなる、...


住宅環境整備(30-5)
1年間、専門学校の「住宅福祉コーディネーター科」に通っている時に、福祉住環境コーディネーター検定を受験しました。そのテキストのはじめのページに、当時、日本大学理工学部の教授でいらした野村 歓先生の文章が載っていました。私はその言葉しびれました。そして、野村先生の講義を聞きた...


住宅環境整備(30-4)
1999年、専門学校に通い始めました。夜のコースは18:30から21:00まで。あの時はまだ母がいて、後押ししてくれました。 楽しかった。同じコースをとったのに、それぞれにきっかけも、状況も、目的も、知りたいことも違う。でも、共感できるし、してもらえる。...


住宅環境整備(30-3)
どうしたらもっとうまく暮らせるだろう、と考え、考えしている時に、1冊の本に出合いました。 町田ひろ子著「インテリアコーディネーターになれる本」 インテリアコーディネーターというと、ホテルやショールームを華やかに飾る仕事だと思っていました。しかし、インテリアコーディネーターと...


住環境整備 (30-2)
どうしたらもっと家の中が使いやすくなるだろう。私はその時々で、メジャー片手に夢遊病者のように家の中を歩き回りました。 父は左手しか使えません。手の長さや歩幅、その動きを予測して、必要な家具や道具をどの位置に、どの向きで置くか。母の介助の負担を少なくするには、何をどう置くか。...


住環境整備 (30-1)
父が脳塞栓で倒れたのが61歳。定年退職の1年後でした。退職金で払うものは払い、長い転勤生活で買うことのなかった応接セットや立派な座卓や水屋ダンスなども買い、悠々自適な暮らしが始まった矢先の急展開でした。なので、大きな家具が増えたところにあらたに介護ベッドや車椅子が増えるわけ...


新しい暮らし(29-2)
新しい暮らしが始まりました。 父をデイサービスに送り出して、一人座敷に座った時、 「あぁ、やっと止まった…」と、思いました。 滝に打たれたことはないけれど、たぶんそんな感じ。頭から冷たい水がひたひたと体の中に沁みえこんでいくような感覚がありました。...


新しい暮らし(29-1)
退職の日、お昼に送別会もしていただいて、お花もいただいて、普通に勤めきることができました。それは、当たり前のことだけど、私には精一杯。綱渡りでようやく向こう側にたどり着いた感じでした。 よくやったね、と言ってくれた友人もいたけれど、多くは「そう…」とちょっと残念そう。私はと...