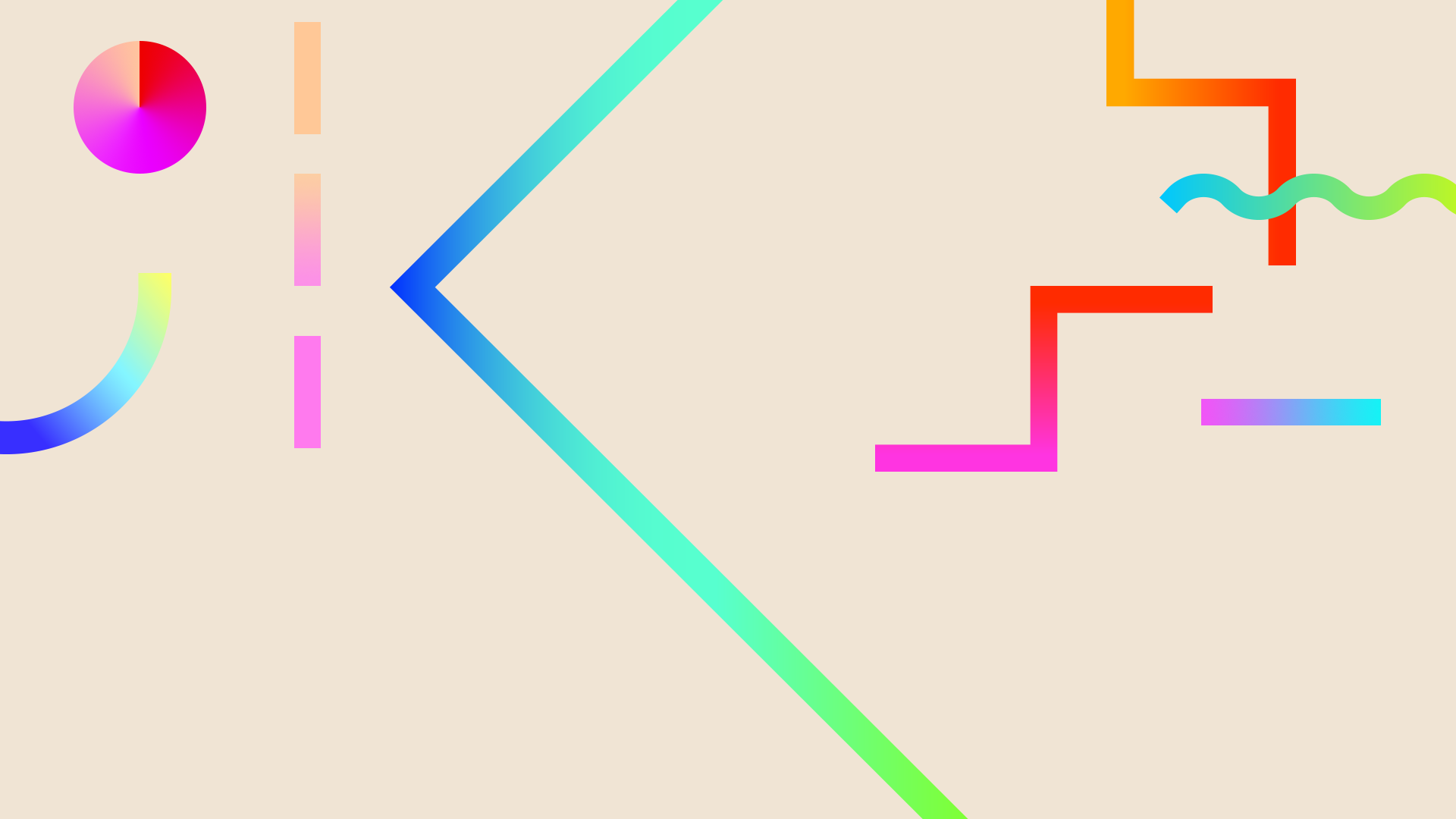電気&人感センサー(32-1)
歳を重ねるという変化。できるだけ昔と同じようにと頑張ることももちろん大事。だけど、それだけではだんだん苦しくなってきます。これまでの方向を少し変えたり、新しい物を取り入れたりすることで、それまでの暮らしが維持しやすいように思います。...


要る / 要らない / 保留(31-4)
父は左側に杖や手すりがなければ、一歩も歩くことができませんでした。その父が在宅で暮らすためには、住環境を父の身体機能に合わせながら生活することが必要不可欠でした。そして、母が亡くなり、妹が結婚して家を出て、父と二人になった時、仕事もあって、すべてを早くやらなければならなかっ...


要る / 要らない / 保留(31-3)
今の年齢になるのはみんな初めてで、昔なったことがあると言う人は一人もいません。体調や体の動きが何か今までとは違うなぁと感じると不安になります。そんな時、一番大きいサイズのゴミ袋を片手に、まずは引き出し一つ分空にしてみませんか。気分転換&新しいスペースが少し不安を解消してくれ...


要る / 要らない / 保留(31-2)
2008年、仕事を辞めてから取りかかった家の片付け。 まずは確認。 開けたことのないところを開けてみる。椅子にのらないと見られない天袋とか扉の中を開けてみる。経年劣化であきらかに使えなくなってしまったものを始末する。これだけでもだいぶスッキリします。...


要る / 要らない / 保留(31-1)
2008年、仕事を辞めました。そして、まず取りかかったのは、父と私の今の暮らしに合うように物を片付けることでした。2002年に母が亡くなるまで、自分の部屋以外は母が統治していましたから、開けたことのない天袋はいくつもありました。...


クレソン摘み
1994年の3月、父が脳塞栓で倒れて少したった頃、ちょうど今の季節、大学の同級生二人が父の見舞いに来てくれました。そして、病室から片時も離れられずにいる私を、病院からそう遠くない湧水の小川に連れ出してくれました。 早春の柔らかな緑、陽は西に傾き始めていました。...


住宅環境整備(30-6)
母の応援もあって、社会に目を向ける機会を持ちましたが、その母が2002年急逝しました。それからのすったもんだは、これまでお伝えしてきた通り。自分の生活の中に父の生活がすっぽり入る形になりました。そんな時間と経験を経て、また生活の形は変わりました。さてさて、これからどうなる、...


住宅環境整備(30-5)
1年間、専門学校の「住宅福祉コーディネーター科」に通っている時に、福祉住環境コーディネーター検定を受験しました。そのテキストのはじめのページに、当時、日本大学理工学部の教授でいらした野村 歓先生の文章が載っていました。私はその言葉しびれました。そして、野村先生の講義を聞きた...


住宅環境整備(30-4)
1999年、専門学校に通い始めました。夜のコースは18:30から21:00まで。あの時はまだ母がいて、後押ししてくれました。 楽しかった。同じコースをとったのに、それぞれにきっかけも、状況も、目的も、知りたいことも違う。でも、共感できるし、してもらえる。...


住宅環境整備(30-3)
どうしたらもっとうまく暮らせるだろう、と考え、考えしている時に、1冊の本に出合いました。 町田ひろ子著「インテリアコーディネーターになれる本」 インテリアコーディネーターというと、ホテルやショールームを華やかに飾る仕事だと思っていました。しかし、インテリアコーディネーターと...